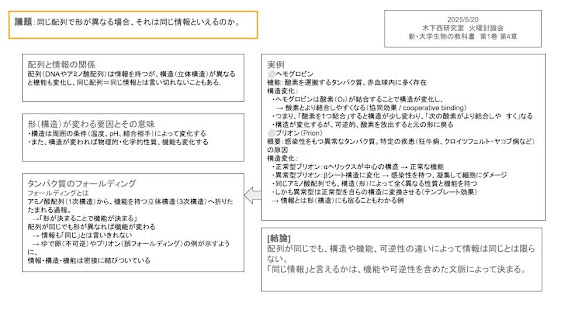【議題】生態系サービスの経済的な価値を考えるとき、重要なことは何か。
2025年12月26日金曜日
大学生物の教科書 第5巻 第26章 生態学的群落(コミュニティ)
2025年12月16日火曜日
大学生物の教科書 第5巻 第25章 生物種間相互作用の生態学的・進化論的意義
【議題】侵略的な生物種をコントロールするために意図的に生物種を導入するときの注意点は何か。
【結論】生物種の導入は、生態系と連鎖的影響を十分に把握し、制御可能であると判断できる場合に限り許容される。導入前には、パイロット環境での実験・空間/時間スケールの検討・捕食者/被捕食者双方への影響評価が必須であり、導入時にも、放つ数の制限・GPSやチップによる管理・去勢による個体数制御を組み合わせることが重要であると考えられる。
大学生物の教科書 第5巻 第24章 個体群
【議題】地球上における人類の平衡サイズKの範囲はどのように推定できるか。
【結論】Kを制限する条件として化石燃料の量など、Kを変動させる条件として食糧生産の技術や医療技術などがあることが挙げられた。これらの条件を式に組み込む際には、その時間変化や重み付けを考慮する必要があることが指摘された。また、現実の人口推移に照らしてこれらの条件が実際にどのように作用してきたかを確認し、Kの取りうる範囲を推定することが重要であると指摘された。
2025年12月4日木曜日
大学生物の教科書 第5巻 第23章 環境における生物
【議題】もし人間が南西オーストラリアに窒素(肥料など)を過剰に供給したらどうなるか
【結論】窒素が増えるとイネ科の植物が入ってきた場合に山火事のサイクルが早くなり、在来植物は成長速度が追いつかず、外来植物が生き残って生態系が変わる可能性が高い。
2025年12月1日月曜日
大学生物の教科書 第4巻 第22章 動物の進化と多様性
2025年11月18日火曜日
大学生物の教科書 第4巻 第21章 地球上における生命の歴史
【議題】環境依存の生命の進化を考えた時、知的生命はどのようにしてそれに向き合っていくべきか。
2025年11月11日火曜日
大学生物の教科書 第4巻 第20章 種分化
2025年11月4日火曜日
大学生物の教科書 第4巻 第19章 系統樹の復元とその利用
【議題】 未知の病原体のヒトへの感染リスクをどのように評価できるか。また、その知見をどのように活用するか。
【結論】未知のウイルスへの感染リスクは、系統樹解析により推定できるが、既知のウイルスの情報に依存していることに加え、実際にヒトへ感染するかは実験的検証が必要であるという問題がある。そこで、AI解析や構造予測などの他の手法を組み合わせて評価し、接触率や重症度なども考慮して総合的にリスク評価を行うことが重要となる。また、このようなリスク評価による知見を用いて、感染リスクの高いウイルスに優先的に対策を講じることが求められる。
2025年10月30日木曜日
大学生物の教科書 第4巻 第18章 進化のメカニズム
【議題】ヒトも、高温に耐えることができる遺伝子型を持つことで、地球温暖化に対応することができるのだろうか。また、それは実現可能なのだろうか。
【結論】HPSの活性化や、発汗に関わる遺伝子を調整することである程度は地球温暖化にも対応できそう。コリアスチョウのような特定の生物における酵素をヒトに取り込んでも、同じように酵素が働かないため、高温に対する耐性は上げることは期待できない。
2025年10月27日月曜日
【議題】成長が個体の一生を通して続く生物、途中でほぼ安定した最終点に到達する生物の違いは何か。
【結論】成長が個体の一生を通して続くか、途中で止まるかの違いは、生物がどのように体温と代謝を制御しているかによる。
恒温動物では性ホルモンが成長を止める一方、変温動物や植物は環境要因に応じて成長を続ける。
➡ この違いは、生物が進化の過程で獲得した成長戦略の多様性を示している。
2025年10月15日水曜日
新・大学生物の教科書 第3巻 第18章 組換えDNAとバイオテクノロジー
【議題】組換えDNA技術の医療応用は、どこまで許されるべきか?
【結論】
組換えDNA技術の医療応用として医薬品開発と遺伝子治療があり、ある程度実用化されている一方で、ゲノム編集技術と生殖細胞の遺伝子治療は技術的・倫理的課題があり臨床での医療応用は実用化されていない。将来技術的安全性が認められた場合、体細胞の編集は実現しそうだが、生殖細胞の改変は遺伝的多様性の問題や責任問題などの課題がある。
2025年10月7日火曜日
新・大学生物の教科書 第3巻 第17章 ゲノム
【議題】精密医療における環境データはどんな問題を含んでいるか? また、それを改善するには何が必要か?
【結論】
医療における環境データは、恒常的ではないこと、データの収集にバイアスがかかってしまうことが問題点として挙げられる。特に、精密医療においては、遺伝子データに比べて根拠が弱く、データ間の相互作用を評価するのが難しいことが問題である。
現時点で完璧な解決は難しいが、環境要因が大きい疾患に対しては、環境データが重要であるため、環境データを客観的なデータにすることで医師の意思決定に役立てることができ、議題の解決に役立つと考えられる。
2025年10月6日月曜日
新・大学生物の教科書 第3巻 第16章 光合成:日光からのエネルギー
【議題】FACE実験の知見をどのように活用できるか。
【結論】FACE実験の知見は、将来の食料生産や植生管理に活かせるが、CO₂濃度だけで判断せず、温度、水分、窒素栄養などを含めて総合的に活用すべきである。
2025年9月24日水曜日
新・大学生物の教科書 第3巻 第15章 化学エネルギーを獲得する経路
【議題】短距離走と長距離走ではどの代謝経路が重要か
【結論】短距離走では、即座にエネルギーを取り出す必要があるため、クレアチンリン酸が十分な量貯蔵されていることや、速筋が発達していることが重要である。長距離走では、有酸素系が最も働くため、ミトコンドリア含有量の多い遅筋の発達が重要である。グリコーゲンをたくさん摂取するなどがいい準備として考えられる。
2025年7月29日火曜日
新・大学生物の教科書 第3巻 第14章 エネルギー、酵素、代謝
【議題】酵素機能を持つRNAが存在することの利点を考える。
【結論】現代ではタンパク質酵素の方が優れており、RNA酵素の利点はあまり感じられなかった。
ただ、生命の起源や進化の過程を考える上では重要な存在だと思う。
2025年7月24日木曜日
新・大学生物の教科書 第2巻 第8章 細胞周期と細胞分裂
【議題】ゲノムが同じで染色体数が多い個体と少ない個体のメリットデメリットを考える
【結論】ゲノム長が一定で染色体数が少ないときに起こり得ることを挙げ、種の生存に対してのメリットとデメリットに分類した。デメリットの方が多く挙げられたが、染色体数が多い場合にはトリソミー疾患が増加するなどの問題点が指摘された。
2025年7月22日火曜日
2025年7月14日月曜日
新・大学生物の教科書 第1巻 第6章 細胞膜
【議題】淡水魚が相当量の化学エネルギーを使ってまで周囲環境と異なる内部環境を持つのはなぜか
【結論】
淡水魚がエネルギーを使って環境と異なる内部環境を持つのは、生命活動を維持するためである。海で誕生した等張な魚類の祖先が淡水へ進出する過程で、環境と体内の浸透圧差に対応する必要が生じ、内部環境を維持する仕組みを獲得した。
2025年7月8日火曜日
新・大学生物の教科書 第1巻 第5章 細胞:生命の機能単位
【議題】モータータンパク質はどのようにしてその複雑な働きを実現しているのか。またその働きをモデル化できるか。
【結論】モータータンパク質が小胞を運ぶプロセスや、動くメカニズムを具体的に解明できればモデル化できるのではないか。
2025年6月30日月曜日
新・大学生物の教科書 第2巻 第13章 遺伝子変異と分子医学
【議題】女王バチになるかどうかを、なぜ遺伝子配列のみで決定しないのか?
【結論】女王バチになるかどうかは遺伝子配列「だけ」では決定しない。同じ配列でも、発現の仕方によって異なる性質・役割を持つ。このようなEpigeneticsは、進化的にも合理的で、社会性昆虫のような複雑な集団生活において、柔軟性と安定性をもたらしている。
2025年6月18日水曜日
新・大学生物の教科書 第2巻 第12章 遺伝子変異と分子医学
【議題】変異原や発がん性物質を生産する生物は、その物質からどのように自分自身のDNAを守るのか?またそのメカニズムを治療や予防に応用できるか。
【結論】アスペルギルスのような変異原を生産する生物の自己防衛メカニズムは完全には解明されていないものの、複数の仮説がある。変異原に対する防衛メカニズムを用いた治療や予防への応用を考える上では、酵素による無毒化やDNA修復機構の強化が有望である。
2025年6月10日火曜日
新・大学生物の教科書 第2巻 第11章 DNAからタンパク質へ:遺伝子発現
【議題】遺伝子発現が一方向であることの意味。または一方向でなかった場合の世界線について。
【結論】もし遺伝子発現が双方向であり、RNAからDNAへの逆転写が普遍的に存在したと仮定すると、有性生殖か無性生殖かによってその影響は大きく異なると考えられる。特にヒトの場合、両親から子孫へ安定した遺伝情報が正確に受け継がれにくくなり、種として安定的に子孫を繁栄させることが困難になったと考えられる。したがって、遺伝情報の正確な伝達と安定性を確保し子孫を繁栄させるため、一方向性の遺伝子発現が基本として確立されてきたと言えるだろう。
2025年6月3日火曜日
2025年5月29日木曜日
新・大学生物の教科書 第2巻 第9章 遺伝、遺伝子と染色体
【議題】プラスミドを介した抗生物質耐性遺伝子の転移を防ぐにはどうしたらいいか。
【結論】ヒトにおいては抗生物質耐性遺伝子の転移を防ぐことは難しい。現実的にできることは、抗生物質やプラスミドの複製阻害剤などを使用して、抗生物質耐性遺伝子の広がりを防ぐこと。
2025年5月26日月曜日
2025年5月14日水曜日
新・大学生物の教科書 第1巻 第3章 タンパク質、糖質、脂質
【議題】L-アミノ酸の選択のようなホモキラリティは生物にとってどのような意味があるか
【結論】アミノ酸や糖質などミクロの視点では安定と効率の面でホモキラリティが重要である。臓器などの偏りについてはミクロな偏りが要因の一つかもしれないが、一般化はできない。
2025年5月8日木曜日
新・大学生物の教科書 第1巻 第2章 生命を学ぶ 生命を作る低分子とその化学
【議題】水の性質は他の惑星でも生命を支えるのか?
【結論】他の惑星では水の性質(惑星Xの気温で液体であること、極性をもつこと)が働かなくなるため、水は生命を支えるとは限らない。ただし、他の惑星(地球と異なる環境)で、水と似た性質をもつ物質があれば生命を支える可能性はある。
2025年4月16日水曜日
新・大学生物の教科書 第1巻 第1章 生命を学ぶ
【議題】突然変異が起こる環境因子を人間が制御することはできるのだろうか。
【結論】人間が環境因子を介入・制御することで、一部の外的要因による突然変異の可能性は低減できる。しかし、ゲノム複製自体の不完全性や宿主内の生理的反応(ストレスや活性酸素の増加)に起因する突然変異は、依然として発生するリスクがある。

.png)













.png)




.png)